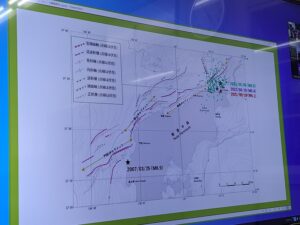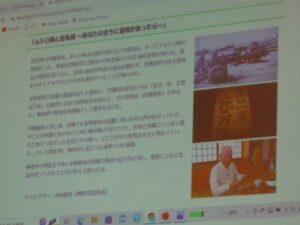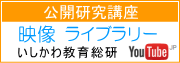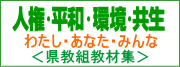教科書採択の会議公開を求める
小松市教育委員会に市民から集めた署名を提出するとともに、会議の公開を要望しました。中学生が来年から4年間使用する教科書を、各市町の教育委員会が今年は決める年になります。前回の2020年小松市では選定委員会ではじめに推薦されなかった教科書が教育委員会会議で採択されました。このときの結果には疑問が生じ、文科省の通知にもある説明責任を果たすには審議の過程や理由を明らかにする必要があります。全国的にも公開する教育委員会が増えています。静謐な環境が求められるのであればオンラインによる公開という方法もあります。
「教科書採択に関わる会議の公開を」要望書は左をクリック


 環境教育フィールドワーク(美川安産川はりんこの池)
環境教育フィールドワーク(美川安産川はりんこの池)