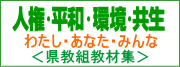2019年度 県自治体における教育予算等の調査結果
「子どもの貧困対策」関連自治体施策
「奨学金制度」何らかの制度を持つ自治体14/19、内9が給付型
「就学援助」 県平均小学校11.9%、中学校13.9%
1.経過と現状
(1)2017年6月、厚生労働省が発表した2016年「国民生活基礎調査」で日本の子ども(18歳未満)の相対的貧困率※は、13.9%(7人に1人)となった。調査は3年おきになされており、過去最低だった前回より、2.4ポイント下がり12年ぶりに改善したという。ただ経済協力開発機構(OECD)の直近のデータによれば、加盟36カ国の平均は11.4%であり、日本は加盟国のうち、データのある34カ国中20位と依然低位にある。
※「相対的貧困率」国民一人ひとりの所得を高い順に並べ、真ん中の所得の半分(貧困線)に満たない人の割合をいう。
(2)2014年1月17日に施行された「子どもの貧困対策の推進に関する法律」(以下、貧困対策法)。法の目的は「子どもの将来が、生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、対策を総合的に推進すること」とされている。
この貧困対策法は5年をめどに見直すことになっており、2019年9月7日に改正案が施行された。この改正案では、貧困状況の子どもや保護者の意見を反映させることを明記、ひとり親世帯の貧困率と生活保護世帯の子どもの大学進学率の2つの指標と改善策を政府の対抗に記すよう求めた。加えて、所得増加につながるよう、保護者への就労支援を進めることも盛り込んでいる。
(3)授業料以外でも私費負担が多額になっている。一般的な返済を必要とする貸与型奨学金は04年度に制度改変し、独立行政法人「日本学生支援機構」に所管が移行した。機構の奨学金は無利子と有利子の2種類で、貸与された奨学金の返済は卒業して6ヶ月後から始まり、20年で返還となっており、就職の可否に関わらず、3ヶ月滞納するとブラックリストに載せられる。2017年度の総貸与残高は9兆4千億円、返還者は426万人、3ヶ月以上の延滞者は16万人、卒業時の平均貸与額は無利子で240万円、有利子で340万円となっている。
そうした中、文科省は2017年度から返済の必要がない給付型奨学金の支給を始めた。対象は大学等の進学を希望し、住民税が非課税となっている世帯が対象で自宅通学月2~3万円程度、自宅外で6~7万円となっている。初年度の2018年度は約18,000人程度、2019年度で21,000人程度が受給している。ただ必要としている全ての学生には行き渡らず、給付額も大学に通うには十分とはいえないと指摘もあり、引き続き課題となっている。
(4)就学援助は、生活保護世帯と、それに準じて生活が困窮している「準要保護」の子どもが対象となっており、生活保護世帯は国が補助、準要保護は市区町村が平均年7万円相当を補助している。2015年度では小中学生全体の15.2%を占めており、2010年度以降、15%以上の高止まりになっている。国が13年度から3年間で生活保護費の内、生活扶助分を6.5%切り下げて以来、2018年度10月からさらに生活扶助を中心に(最大5.0%減)引き下げている。基準を下げたことで就学援助対象者にも影響することとなり、自治体が定める基準(概ね生活保護基準の1.3倍)の見直しが迫られている。こうした「子どもの貧困率」の増加は財政状況の厳しい自治体負担が大きくなる傾向もあり、自治体間にバラツキが出ていると言われている。貧困対策法の趣旨を生かすには、自治体に運用を任せるのではなく、補助金の確保、所得制限の緩和、援助費目や金額の拡充がより一層必要となる。
(5)文科省が10月に発表した「不登校」(年間30日以上欠席)は、小中学校で164,528人と前年度比で20,497人増加、6年連続で増加している。教育総研では、県内状況を把握できないかと、新たに実態報告をお願いしたが、多くの自治体から「統計法」を根拠に公表できないとされ、集計は叶わなかった。
詳細はこちら