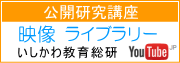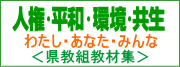〇教育政策部会では、2022年に開設した公立中学校夜間学級について三豊市教育委員会から説明を受けた。学びの多様化学校(不登校特例校)として初めて学齢期の生徒を受け入れた。外国籍や様々な年代の学齢経過者の方々と共に授業を受けることにより、相互の違いを知り差異を受け止め自分自身を変容させたり、生活の知恵を身につけたりすることができた。また、同世代の同調圧力や学力優先の雰囲気がなくのびのびと学習ができている。
「三豊市における公立夜間中学について」資料は左をクリック
〇平和教育部会では、小南部会長が今年度の選挙を振り返った。衆院選では自公連立政権が過半数割れとなり、国会での審議もこれまでと異なり予算成立にも野党の意見が取り上げられている。一因としての自民党裏金問題は共産党「赤旗」が暴いたものであったが、マスメディアの権力監視機能は低下している。メディアコントロールと自主規制が進み、テレビの選挙報道は減少してきた。総選挙の投票率は戦後3番目の低さであった。世代別では70代は7割を超えているが年齢が下がるほど低くなっている。日本の教育は「社会の変え方」を教えておらず、子どもたち自らが参加したり意見を表明する経験が乏しい。子どもの権利条約やこども基本法の理念を活かした教育が求められる。
「政治を変える力・政治に参加する力を!」資料は左をクリック
〇半島震災では二重孤立として集落へのアクセスが寸断されることと半島への3つの幹線道路が交通障害を起こしてしまったことがあった。能登地域での高齢・過疎の問題が被害の拡大・長期化の要因ともなった。建物の崩壊は新しい耐震基準では防げており古い家で下敷きとなり亡くなっている。珠洲の人口は3割減っているが仮設住宅に残った高齢者が寿命を迎えると減少が進んでしまう。公営復興住宅は土地の確保も進んでおらず若者が早く戻れるようにしなくてはならない。能登の学校で起こったことを教訓として加賀の先生も知り今後の防災教育に活かすことが課題である。